トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 糖尿病内分泌代謝科 > 診療のご案内
診療のご案内
糖尿病など代謝の病気
糖尿病について
当科では10名の糖尿病専門医のもとに、糖尿病を診療する外来が平日の毎日開かれています。
糖尿病には網膜症・腎症・神経障害という特徴的な合併症がありますまた糖尿病は動脈硬化が進みやすく、それに伴って心筋梗塞・脳卒中が起りやすい病気でもあります。糖尿病の合併症等の診断、治療の過程で腎臓内科、眼科、神経内科、循環器科、心臓血管外科などと密に連絡をとって、的確な医療を目指しています。
また小児期に糖尿病を発症した方が成人になられたことを期に小児科から内科へ診療をバトンタッチしたり、妊娠時の糖代謝の異常(糖尿病の方の妊娠・妊娠糖尿病)を産婦人科との連携のなかで診療しています。
糖尿病以外の代謝疾患について
脂質異常症(コレステロールや中性脂肪が高い方、HDL(善玉)コレステロールの低い方)、肥満など生活習慣とのかかわりが強く、動脈硬化が進みやすい病気に対し、生活習慣指導を行い、必要な検査・治療を行っています。
糖尿病など代謝の病気の検査
血液・尿検査
糖尿病など代謝の病気は、自覚症状がないままに、合併症が進むこわい病気です。外来では体重・血圧のチェックとともに血液検査によって血糖・HbA1c・コレステロール・中性脂肪などを(必要に応じて肝機能検査・腎機能検査なども)、尿検査によって尿タンパク・尿糖などを計ります。
専門的な検査
動脈硬化の度合いを調べる検査として頚動脈超音波検査や脈波伝播速度(PWV)、足関節上腕動脈血圧比(ABI)をうけることができます。CT・MRI検査などは放射線科に依頼して実施しています。
糖尿病の教育・治療入院
当科では、糖尿病の教育・治療入院を実施しています。

- 生活習慣病教室、糖尿病教室に参加:医師・看護師・薬剤師・管理栄養士から直接指導がうけられます。
- 高性能の歩数計をつけていただき、入院中の運動量をデータ化することで、運動療法が適切に行われているかを視覚的に理解できます。
- 糖尿病に合併する疾患(高血圧・脂質異常症・糖尿病腎症)の評価を行ないます。
- 糖尿病・ (コレステロール、中性脂肪に異常のある病気)などの治療薬の調整をいたします。
生活習慣病教室・糖尿病教室のご案内
当センターでは、院内の各科担当スタッフによる生活習慣病教室と糖尿病教室を隔週ごとに、交互に実施しています。
- 当センターにご入院、通院中の方だけではなく、どなたでも参加いただけます。
- 事前予約は不要です。1コマだけでも参加できます。
- 受講料は無料です。ただし、「お食事の話」(生活習慣病教室木曜日、金曜日;糖尿病教室火曜日)については、入院中の方のみ入院費に加算されます。
- 受講者カードをお配りし、すべて参加された方には、受講修了証をお渡ししています。
- お問い合わせ先:当センター病院 教育指導室 電話番号: 03-3202-7181(内線2568)。
生活習慣病教室の講義内容(一部抜粋)
詳しくは生活習慣病教室のページをご覧ください。
- 自分はまだ大丈夫?生活習慣病
- つらい目、避けよう―生活習慣病と眼のかかわり―
- 高血圧・動脈硬化の食事―塩分制限が大切です!―
- 血管注意報!高血圧、心臓病、動脈硬化について
- 病院の薬は恐い?恐くない?生活習慣病のお薬
- 見逃さないで、その症状(脳梗塞のお話)
- 座ってできるストレッチ体操
- 肥満にまつわる話題(メタボ体型って何?)
- 生活習慣病は検査が発見してくれる!(検査のお話)
- 知っておこう。腎臓の働きと糖尿病性腎症
糖尿病教室の講義内容
詳しくは糖尿病教室のページをご覧ください。

- 「糖尿病」って何?
- 糖尿病食は健康食!
- 検査からわかる糖尿病
- 素敵な足をめざして♪ ―糖尿病の足の病気の予防―
- 知っていますか?自分のお薬
持続血糖モニター(CGM)
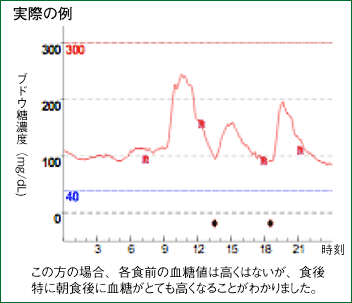

CGM装置

より小型化したCGM装置
甲状腺など内分泌の病気
当科には3名の内分泌専門医のもとに、甲状腺(バセドウ病や橋本病)・副甲状腺・副腎・下垂体などの内分泌の病気を診療する外来が平日の毎日開かれていま す。内分泌の病気については、必要な場合には当科と同様にこれを専門とする小児科・耳鼻科・産婦人科・泌尿器科・脳外科各科と協力して診察しています。例 えば妊娠中・出産後の甲状腺の病気は産婦人科と、副腎の腫瘍は泌尿器科と、脳下垂体の腫瘍は脳外科と連携しています。
内分泌の病気の検査
基本的なホルモンの検査(血液検査)は外来で行います。 一部の特殊なホルモン検査については予約受診日の1週間前に検査していただ くことがあります。 甲状腺の状態を観察する甲状腺エコーは外科もしくは耳鼻科にて、シンチグラム検査は放射線科に依頼して実施しております。 病気の内容によっては診断と治療方針を決めるため、さらに詳しく検査をするため入院が必要な場合もあります。